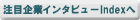「顧客対応力」をビジョンに飛躍する
翼システムが「変革期に求める人材」とは
1990年代初めに始まった「オープンシステム化」は、当初企業の情報系システムに浸透し、企業においてUNIXシステムを一般的なものにした。この環境下に登場したのがJavaだ。J2EEの登場は、インターネットによるWebシステムの構築という形を取り、企業システムの開発のあり方や開発スタイルを一変させた。
それから10年が経ち、オープンシステムは、確実に企業の基幹系システムにも浸透し始めた。そうした激変の様相を呈するIT業界において、真っ先に基幹系システムのオープン化に取り組む翼システム。次世代の企業システム環境を見据え、彼らが抱く事業戦略とは何か? そして変革の担い手として求める人材像とは?
| Java、ミドルウェアの分野で 真っ先にオープン化に着手 |
1990年代前半から始まった「オープンシステム化」の波は、クライアント/サーバ(C/S)型システムの登場によって、徐々に情報系システムに実践されていった。その後、Java、J2EEアプリケーションサーバの登場やERPパッケージの普及などを背景に、いよいよ基幹系システムにもオープン化の波が押し寄せてきた。
ところが日本企業の基幹システムのオープン化において、請求書、見積書、仕入伝票……など「帳票」がネックになることがある。それは印刷フォームや印字品質など、対応するプリンタごとに微妙にカスタマイズすることが求められるからだ。こうした問題を抱える帳票分野にいち早くソリューションを提供したのが翼システムだ。
日本は、日本人が持つ独自の美意識も手伝って、帳票を通じていかに相手に情報を正確に伝えるかということに最もこだわりを持つ国でもある。かつて、パッケージベンダとして「伝票丸」という帳票ソフトを販売していた翼システムにも、帳票のデザインなどに関する顧客からの要望が相次いでいた。
「伝票系の印刷ツールとしては、翼システム株式会社では伝票丸というツールを活用してお客様の各種帳票カスタマイズ要件に対応していました。伝票系の帳票開発であれば、伝票丸は十分な機能を有していましたが、顧客のニーズを踏まえれば、もう少し守備範囲の広い帳票ツールが必要であり、この要件は海外発のソフトウェアでは絶対にできないだろうと判断したのです」と、情報企画事業部部長の内野弘幸氏は当時を振り返る。1992年のことだ。
 |
| 翼システム株式会社 情報企画事業部 部長 内野 弘幸氏 ■明治学院大学経済学部卒業後、多摩ユーザック社に入社し、オフィスコンピュータの営業およびSEに従事。1992年、翼システム株式会社に入社し、企画営業を担当。1995年に帳票ツールビジネスを開始 |
ここに「帳票の翼システム」飛躍の出発点があるといっていい。しかも幸いなことに、絶妙のタイミングで、プリンタ制御技術を有する株式会社エフ・アイ・ティと出会い、翼システムはいよいよ帳票ソフト市場へと本格的に打って出ることになる。1995年には、ノンプログラミングの帳票設計をコンセプトに、従来の伝票丸を作り変え、「Visual Formade For Report」という商品を発売する。
「当時、帳票ソフトには欧米の文化をベースにした製品はありましたが、われわれはそれでは満足できなかった。そういう点で、まったく新しいジャンルで行こうと決めたのです。例えばフォームに対するこだわり、印字品質に対するこだわり。当時、Windows環境でプリントアウトすると、プリンタの機種によって罫線の太さなどが微妙にずれたのです。そうすると、いろいろな機種を入れている大きな会社では非常に困ったことになる。その問題を解決するために、独自にプリンタドライバを作りました」(内野氏)
このようにプリンタメーカーごとのドライバ対応などを丹念に行ってきた結果として出てきたのが、「帳票出力管理ミドルウェア」の世界だ。
「オフコンであれば、アプリケーションに必ず印刷結果を返します。こうしたオフコンの世界からは信じられないことですが、オープンシステム市場にはプリンタをコントロールするミドルウェアがなかったのです。そこで開発したのが、『Report Director』という、プリンタの状態を監視するソフト。これはわれわれにとって、いわゆる帳票設計ツールベンダから印刷総合ソリューションカンパニーになった瞬間でした」
この時点から顧客に対する翼システムの提案エリアは一気に広がり、SAPのR/3のような大企業の基幹業務系のオープン環境でのプリンティング業務というターゲットにもピタリと適合していった。
そこで、さらに課題として出てきたのが、「マルチプラットフォーム化」だ。UNIX対応を迫られる中、必然的に出てきたのがJava化である。そして、早くからJava対応することで製品群がどんどん膨らんでいき、総合的な帳票ソリューションが出来上がっていく。それとともに、翼システムの知名度が確立されていった。
| データ入力から出力 分析機能まで事業領域を拡大 |
いまや「帳票」の分野では、同社は確固たる地位を築き上げている。しかし、急速に進む電子フォーム化の波は、同社の顧客の中にもこれまでとは異なるニーズを生んでいる。
「これまでは人に伝えるために、アウトプットするフォームとして製品を出してきたわけですけれど、顧客の中から『帳票を画面で確認したい』『プレビューで確認したい』、あるいは『プレビューでもう十分だ』という新たなニーズが出てきました。それを知ることによりわれわれの意識も随分変わりました。アプリケーションの世界には、入力(インプット)画面があって出力(アウトプット)の帳票がありますが、これらはそれぞれ異なるデザインフォームです。でも、人間の思考からいって、本来は書き込むフォームと出力するフォームは一緒の方が分かりやすいはずです」
 |
| 翼システムが唱える「オープンサイジング」。これにより、大幅な開発工数の削減やシステムの安定運用が可能になるという |
こうして、データの入り口部分も事業分野に決めたことが、大きな事業ステージの変化となる。入力機能と出力機能、すなわちデータのINとOUTを扱うことになり、アプリケーションにおいて事業分野の幅が拡大していったのだ。
こうした環境の変化に伴い、「情報をどう伝えるか」が新たな事業テーマとなるのは自然な流れだろう。2001年4月には、大規模な多次元高速集計/レポーティングツール「Dr.Sum」を発売した。この商品は、これまでデータマートを追加・更新する際に不可欠とされてきた難易度の高いスキーマ設定を簡便化し、エンドユーザーが気軽にデータを分析できる世界を実現した点に大きな特徴がある。データ集計・データ出力機能に特化したDBエンジンといってもいいだろう。
このように、ユーザーにとって使いやすい帳票フォームや出力というところから、次第にその情報を取り出す「分析機能」まで事業領域を広げてきたが、それでも内野氏は「百貨店を開くつもりはない」と強調する。
「われわれのミッションは、情報システム構築支援そのものです。企業における情報システムに必要な素材を構築するためのツール、もしくは製品を提供するベンダであるというスタンスは変わらない。あるコアの部分を持ちつつ、それに関連する周りのものが事業領域になってきたということにすぎない。百貨店のように何でもそろえるつもりはありません」
そこで、翼システムが今後の事業戦略の中核に位置付けているのが「オープンサイジング」路線だ。オープンサイジングとは、特定のOSやプラットフォームに頼るのではなく、開発環境の制約を「オープン」化し、システムや機能を「早く、やすく、粗結合に」つなぎ、組み合わせることでシステム構築を行うものである。それにより大幅な開発工数の削減やシステムの安定運用も実現できる。
| ●翼システム 情報企画事業部の変遷 | |
| 1990 | 伝票丸(DOS版)発売 |
| 1992 | 帳票ソフト市場への本格参入を決断 |
| 1995 | 帳票出力から帳票設計分野へ進出 Visual Formade For Report 発売 |
| 1997 | 帳票出力管理ミドルウェアへ進出 Report Director 発売 |
| 2000 | マルチプラットフォーム化を加速し、Java対応製品を順次発売 翼プリンティング・ラボセンター開設 |
| 2001 | “情報をどう伝えるか”を事業テーマに Dr.Sum 発売 |
| 2003 | 「オープンサイジング」路線を提唱 |
| 技術知識に加えて「顧客対応力」を 持つ人を採用したい |
一方、あくまでベンダに徹するということに、翼システムの採用戦略の基本ポリシーが隠されている。
「スクラッチでシステムをつくることを考えていない。従って、求める人材もまさに柔軟な感覚の持ち主でなければいけない。ゼロから作り上げるようないわゆる“職人タイプ”ではなく、顧客ニーズが本当に分かる人、もっと具体的にいえば、顧客ニーズを聞き出し、さらにそのニーズをどう組み立てればよいかというソリューションを考えられる人が欲しいです」
具体的に人材が必要な職種としては、まず営業だという。「営業といっても、“御用聞き営業”ではありません(笑)。まず、きちんとした技術知識を持っていることが前提です。営業は顧客の矢面に立つわけですから、顧客の考えることをかみ砕いて整理してあげられる人でなければもたない。従って、これまで技術エンジニアとしてやってきたが、いまの仕事に飽き足らない人、自分はもっと顧客と接点を持ちたい、顧客にソリューションを提案したいというように、エンドユーザーのニーズを取ることに喜びを感じるタイプの人が欲しいです」
次に必要なのがコンサルタント。「システムの導入前、営業段階でのプリセールスに近いところと、契約後に、導入についてのディスカッションができる人。従来は当社もあまりやってこなかったのですが、今後は、導入サポートまでやっていこうと考えています。最近はミドルウェアが多すぎて、SIer(システムインテグレータ)も把握しきれず、間違ったインストールをしてしまうケースが多い。ですからわれわれがそこまで責任を持たないと、システム導入の目的が達成できないケースが増えてきたのです」
実際、パッケージベンダ大手のSAPジャパンから発表された事業展開「mySAP All-in-One ソリューション」に帳票関係でジョイントする翼システムの業務内容にも、インストレーション(導入サポート)が含まれている。
「事業領域がより顧客の近くにまできているということです。これまで、大手SIerの陰に隠れていた部分が前面に出て、ユーザーと直接やりとりしなければいけなくなる。当たり前かもしれませんが、われわれにとっては、エンドユーザーが常に主役であり、それを重視するのが当社の特徴なのです」
 |
| 技術知識だけでなく深い知識欲を持ち、「顧客対応力」を持つ人。そうした人材を変革の担い手として熱望している |
さらに、「システム導入後のトラブル対応に当たるカスタマーサポートエンジニア、内部のラボにおけるテクニカルスタッフ、さらに私と一緒にマーケティングができるような人など、各フェイズで一通りの人材が必要になります」と内野氏は語る。
いずれにせよ、翼システムの採用戦略においては「顧客対応力」がキーワードとなる。
「顧客のニーズに対して、どうしたら最適なソリューションであるのかを考えられる人。自分の持っている知識だけではなくて、世の中にもっといい案があるかもしれないということを貪欲に考えられる人、そして、もし世の中に存在しないのならば最後は自分で作ってみようか、と思える人。そんな知識欲の高いマインドを持つ人を待っています」
システムのオープン化を背景に、帳票からスタートし、顧客ニーズとともに着実に事業ステージを拡大してきた翼システム。これから新たな人材を得て、どんな未知の世界を切り開いていくのか、要注目である。
中途採用 募集要項 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
応募方法については、翼システムのWebサイトを参照ください。 |
||||||||||||||||||
翼システム株式会社
企画:アットマーク・アイティ人財局
製作:アットマーク・アイティ編集局
掲載内容有効期限:2003年6日30日
| 企業情報 |
| 翼システム株式会社 ■設立 1983年2月 ■代表者 代表取締役社長尾上正志 ■資本金 1億円 ■売上高 565億円 ※2003年3月期 ■従業員数 2466名(男1868、女598) 情報企画事業部は79名 ※2003年4月時点 ■本社所在地 東京都江東区亀戸 ■事業所数 全国42事業所 ■事業内容: ●コンピュータ帳票設計・出力ツールの開発、販売、コンサルティングサポート ●自動車関連・機械工具・文具事務機・旅行・携帯電話販売・釣用品・玩具・工務店等の各業界向けコンピュータシステムならびにデータベースの開発、販売、コンサルティングサポート ●「カーコンビニ倶楽部」の店舗開発、運営、商品開発、コンサルティングサポート |
| 待 遇 |
| 昇給・賞与 | |
| 昇給年1回(4月)、賞与年2回(7・12月、年度目標達成時には決算賞与あり)、家族手当、退職金制度 | |
| 勤務時間 | |
| 9:00〜17:30 | |
| 休日・休暇 | |
| 週休2日制(日、祝、第2土、年末年始・夏期休暇を含み年間108日)、有給・慶弔など | |
| 勤務地 | |
| 東京(渋谷区渋谷)、大阪(大阪市北区梅田) | |
| 福利厚生 | |
| 社会保険完備、海外研修制度(全員参加)、金貨支給制度(所属部門が月間目標を達成した場合、部門全員に金貨を支給)、フラワーメッセージ制度(ご家族の誕生日に花束をプレゼント)、クリスマスパーティ、リゾート施設・スポーツクラブなど(健康保険組合直営、提携施設) | |
| @IT関連リンク |
| @ITセッション in 翼システムカンファレンス 2003(@ITサイト) 基幹システムのオープン化の現状と課題(@ITサイト) @IT News:コンポーネント・XML・UMLが開く次世代ソフトウェア開発(@ITサイト) Webコンピューティング時代に求められる新しい情報システムと開発スタイル(@ITサイト) |