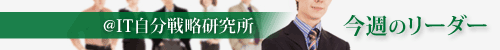
第22回 JPA 牧大輔「モノ作りにこだわればこそリーダーを目指せ」
唐沢正和
大星直輝(撮影)
2009/7/6
 |
| 牧大輔 (まき だいすけ) Japan Perl Association 代表理事 兼 endeworks 代表取締役 1977年生まれ、神奈川県出身 1歳からブラジルで暮らし、日本、ポルトガル、ブラジルなど各国を渡る。米Washington University卒業。2000年新卒で米Network Applianceに入社し、テストツールの作成に従事。これがPerlとの出合いとなる。その後、ネット上のPerlコミュニティで知り会った宮川達彦氏の紹介で2004年ライブドアに入社。米Lehman Brothersなどを経て、2006年endeworks設立。 |
■endeworksは会社というより“工房”
endeworks(エンデワークス)を創業したのは2006年。自社サービス開発を中心に受託開発もしています。社名の由来は、「“en”gineer+“de”signer」でendeworksです。エンジニアが代表の会社ですが、デザイナーと協力してモノづくりをする会社組織です。わたしを含めたエンジニアとデザイナーによる少数精鋭の技術者集団で、“工房”に近いと思っています。
ですから、代表取締役という立場であっても、すべて自分の思いどおりに作り上げるように指示することがわたしの役割ではありません。プロジェクト全体を管理しながら、そのプロジェクトに携わる技術者1人1人が、各分野で最大限に能力を発揮できる環境をつくっていくことがわたしの大きな役割だと考えています。
例えば、わたしが得意ではないデザインの分野については、あまり細かいところまで口出しすることはしません。担当のデザイナーにお任せして、ある程度、自由に作ってもらいます。そうすることで、エンジニアのわたしには思いもよらない発想がデザイナーから出てきたりして、とてもクリエイティブな環境でモノづくりに取り組むことができています。endeworksは職人の集団ですから、わたしがあれこれ指示するよりも、みんながマイペースで自分の力を発揮できれば、必ずクオリティの高いモノがで出来上がってくると信じています。
■Perl技術の実用化を図るべくJPA発足
endeworksを立ち上げたきっかけも、わたし自身がモノづくりを追求していきたいという思いが強かったからです。それはいまでも変わりません。特に、わたしがこだわり続けているのがPerl技術です。endeworksのビジネスを手掛ける一方で、Perl技術の啓蒙・促進活動にも積極的に取り組んでいまして、昨年末にはわたしが発起人となって 一般社団法人Japan Perl Association(JPA)を発足し、今年4月から本格的に活動を開始しています。
そもそも、Perlとの出合いは、2000年にわたしが新卒で入社した米Network Appliance時代までさかのぼります。そこで、テスト担当者向けの支援ツールをPerlで開発したのが始まりです。以来、約10年間、Perl技術者としてのスキルを磨くとともに、年1回のPerl技術者向けカンファレンスである「YAPC::Asia」の運営にも深くかかわってきました。当初、草の根活動的に始まったYAPC::Asiaですが、年々規模が拡大し、昨年には参加者が500人を超えるなど、ボランティアレベルで運営することが難しくなってきました。そこで、カンファレンスの運営母体となるべき法人が必要だと考え、わたしが手を挙げたのがJPA発足のきっかけです。
また、Perlは、コミュニティが中心となって発展してきた技術なので、Javaでいうサン・マイクロシステムズのような旗振り役が存在しません。さらに、技術の根幹にかかわるエンジニアたちも縛られることを嫌っていたため、良くも悪くも技術者指向がとても強い、独自の文化が出来上がってしまいました。その結果、技術的には優れているのに、公式なドキュメントやハイプサイクル、レポートなどが存在せず、企業レベルでは非常に使いにくい技術になっているのが現状です。
一部の企業では、Perl技術者の奪い合いが起こるほど、Perlの有用性が認められているのですが、まだまだ、Perl技術者の活躍の場は限定されています。もっと多くの企業にPerlを使ってもらうためには、コミュニティによる技術者指向の発展だけでなく、誰かが企業での実用化を意識したPerl技術のまとめ役をやらなくてはなりません。この点も、わたしがJPAを立ち上げようと思った大きな理由です。
まだ動き始めたばかりのJPAですが、まずは、セミナーや交流会などの啓蒙活動を中心に展開し、将来的には、Perl技術者の育成や派遣などにも活動を広げ、企業とPerl技術者をつなぐ仲介役としての役割も担っていければと思っています。当面の目標は、9月10、11日に開催する「YAPC::Asia Tokyo 2009」を成功させることですね。より多くの参加者を集め、昨年以上に盛り上がることを期待しています。
■リーダーに付与される責任と権力で、作りたいモノを作る
このように、わたしはendeworksとJPA、2つの組織で代表を務めているのですが、自己分析すると、典型的な創業者タイプなんだと思います。思い立ったら猪突猛進、とにかく自分が先頭に立って、旗振り役をやりたくなるんです。走り始めたら、細かいことを気にせず、どんどん突き進んでいくので、後からついてくる人には苦労をかけているかもしれませんね。ただ、周りがお膳立てしてくれるのを待っていたのでは、いつまでたってもやりたいことはできませんから。
最近のエンジニアは、リーダーのような責任を持たされる立場にはなりたくない傾向があるように感じます。確かに、責任のある立場になると、面倒な仕事も増えますが、それ以上に、モノづくりに対してこだわれる領域が一気に広がるというメリットがあることに気付いてほしいですね。プロジェクトの末端で開発しているうちは、責任がない代わりに、モノづくりにこだわれる領域もほんの一部にすぎません。つまり、リーダーになると、責任とともに権力が生じます。その権力を自分がプランしたモノづくりのために使うことができるのも、大きな魅力ではないでしょうか。エンジニアという、モノづくりにこだわる仕事を目指しているのであれば、リーダーという役割をあえて避けるのは得策ではないと思います。
わたし自身、責任者の立場になってから、自分のやっているモノづくりの価値が見えるようになりました。それまでは、いま自分の開発しているものに一体どれだけの価値があるのか、それがどう成果につながるのか分からずに、どこか納得できないまま仕事を続けていました。末端のエンジニアではなく、モノづくり全体の流れを理解して、それを自分でコントロールしたいと思ったことも、わたしがendeworksを立ち上げた理由の1つです。
ただ、一言でリーダーといっても、いろいろなタイプがあります。上に立ってプロジェクト全体を仕切っていくようなマネージャタイプだけがリーダーではありませんし、それにこだわる必要もないと思っています。わたしのように、自らの技術力を生かして開発にかかわり、プロジェクトメンバーと協力しながらモノづくり全体をまとめ上げていくのも、リーダーの1つの形だと思っています。モノづくりの仕事が本当に好きな人であれば、なおさら、リーダーという役割に積極的にチャレンジしてほしいですね。
@IT自分戦略研究所は2014年2月、@ITのフォーラムになりました。
現在ご覧いただいている記事は、既掲載記事をアーカイブ化したものです。新着記事は、 新しくなったトップページよりご覧ください。
これからも、@IT自分戦略研究所をよろしくお願いいたします。
