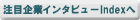プロジェクトを成功に導くマネージャの条件
納期、予算さえ守ればプロジェクトは成功なのか?
テンアートニがマネージャ、マネージャ候補を匿名スカウト中 |
| テンアートニがWebシステム開発プロジェクトを牽引できるマネージャと将来のマネージャ候補を匿名でスカウトします。詳しくは記事の最後をご覧ください |
「プロジェクトの成功とは、納期どおり、予算どおりに開発を終了させることだけではない」と断言するのは、株式会社テンアートニ(以下、テンアートニ)で執行役員 第一事業部長を務める山崎靖之氏。テンアートニといえば、@ITで連載記事を執筆するなど、オープンシステム開発における技術力に定評がある。山崎氏が率いる第一事業部はまさにWebシステム開発の精鋭部隊だ。
では、山崎氏が定義するプロジェクトの成功とは何か? そしてプロジェクトを成功に導くためにマネージャには何が必要なのか? 迅速かつ効率的なプロジェクトマネジメントへの関心が高まる中、プロジェクトマネジメントの実践そして理論にも造けいが深い、山崎氏が語った。
| ステークホルダーを 徹底的に洗い出せ |
 |
| 株式会社テンアート二 執行役員 第一事業部長 山崎靖之氏 1963年生まれ。日本ラショナルソフトウェア株式会社(現日本アイ・ビー・エム ラショナル事業部)のコンサルタントを経て現在に至る。メインフレームの企業情報システム開発から、ダウンサイジングの波とともにUNIX、PCでの開発へシフト。開発プロセスに関しては、メインフレーム時代ではDOA、その後はオブジェクト指向の開発手法に幅広くかかわる。現在はRUPを自社向けに仕立て直し、より実践的にしたプロセス「t-SES(Tenartni Software Engineering Standard)」を作成 |
システム開発の成功が「納期どおりに完成させることではない」ならば、何を判断基準にすればいいのか。
「前提としてROI(対投資効果)で良い結果を出すことに加え、顧客満足を予算内で満たすことです。限られた投資額でも、顧客ニーズを的確に満たしていれば成功といえます。売上向上や人件費削減などに目が向かいがちですが、顧客満足度に着目することを忘れてはいけません」と山崎氏は強調する。
逆に陥りやすい失敗の原因として挙げられるのは、ステークホルダーの洗い出しが不完全であることだ。例えば経営者、財務、営業、エンドユーザーなど、すべてのステークホルダーにヒアリングしたと思っても、「影響がある人物の存在」をすっかり忘れてしまうことがある。
開発工程の終盤でその人物のニーズを満たしていなかったことに気付くようでは遅すぎる。後の祭りになりかねない。「誰がこんなシステムを作れといったのか」と問題になり、当初の計画どおりに進まなくなってしまうのだ。
これは、ステークホルダーの洗い出しが容易ではないことにある。要求を出す企業側も利害関係をすべて把握できているとは限らない。間違った“レール”に乗ったままプロジェクトを進めないようにするには、要求定義のフェイズで完全にステークホルダーを洗い出しておく必要があるだろう。それができるかどうかはプロジェクトの成否を大きく左右することにもなる。
| プロマネが要求定義に関与すれば 投資効率は大きくアップする |
そうはいっても、要求定義をまとめる際のヒアリングはプロジェクトマネージャ(プロマネ)の責務だけとはいい切れない。企業やプロジェクトの規模によるが、「少なくともプロマネが精査の段階で関与する」というのが現実の姿ではないだろうか。テンアートニでは要求のヒアリング役が専任でいても、プロマネは立ち会うことが多いという。
「プロジェクトが千や万人月規模の大きさにもなると、役割分担が細分化されるため、プロマネが要求定義の場に立ち会うことはないでしょう。テンアートニがかかわるプロジェクトは最大でも数百人月ですが、ユーザー企業は四半期や半年でプロジェクトを区切って発注する傾向もあり、規模はその程度で収まることが大半。効率的なプロジェクトの運営が不可欠なため、なるべくプロマネが立ち会うようにしているのです」
要求定義のヒアリングにプロマネが立ち会うかどうかは、それぞれの“社内事情”によるとしても、プロジェクトで無駄な成果物を出さないようにするのは共通の命題だ。要求定義のフェイズで試行錯誤の時間をなくすことは、結果的に投資の圧縮になる。すなわち、要求を的確に管理することが最小限の投資で最大の効果を得ることにもつながるのだ。
| 要求定義には 6つのステップがある |
山崎氏によれば要求定義を細分化すると、6段階に分かれるという。順番に説明すると、(1)問題を分析する、(2)ユーザーニーズを理解する、(3)システムを定義する、(4)開発範囲を管理する、(5)システム定義を詳細化する、(6)適切なシステムを構築する、という6つのフェイズだ(図1参照)。
| ●要求管理に必要な6つのチームスキル |
 |
| 図1 要求のヒアリング段階にプロマネが立ち会えば、(1)〜(4)がブラックボックス化することがなくなる。要求時に誤りを見つけて対処する場合のコストを1とすると、保守段階まで誤りが見つけられなかった場合ではコストは200にもなるという |
こうした手順を知らないと、漠然と頭の中で問題を整理し、いきなりユースケースモデルを書くところから始めてしまう人がいるという。つまり(1)〜(4)を飛び越えて(5)の「システム定義を詳細化する」から始めてしまう。それでは要求定義が不完全なままだ。
(1)の「問題を分析する」と(2)の「ユーザーニーズを理解する」を理解したうえで、(3)の「システムを定義する」に進み、次に優先度を見極めて、(4)の「開発範囲を管理する」に進む。ここまでのプロセスを踏んでから、ようやく(5)の「システム定義を詳細化する」に進めるのだ。
ただ、会社やプロジェクトの規模によっては(1)〜(4)までをコンサルティング会社が担当することもある。その場合プロマネはITコンサルタントなどが作成したレポートを基に(5)から着手する。だが、プロマネが(1)〜(4)の場に立ち会わなければ、そこまでのフェイズにミスがあるかどうかを見極めにくい。
その点、テンアートニでは要求のヒアリング段階にプロマネが立ち会うことが多いため、(1)〜(4)がブラックボックス化することはない。プロマネがコンサルタントの領域にも踏み込み、自らプロジェクトの上流工程に関与し、それをコントロールすることでプロジェクトの成功を確実にすることができる。
「要求時に誤りを見つけて対処する場合のコストを1とすると、保守段階まで誤りが見つけられなかった場合ではコストは200にもなります。多少手間をかけても、上流工程で軌道修正するメリットがあるのです。プロマネがヒアリングに立ち会うのは、コストに直結するリスクを最小限に抑える理由があるからです」
| プロジェクト管理には問題分析力と リスク感覚が求められる |
一方、プロジェクトの成功率を高めるには、PMBOK(the Project Management Body Of Knowledge)など既存のフレームワークを習得することも効果的だと山崎氏はいう。実際にテンアートニのシステム開発では、PMBOKを基にしたチェックリストを用いている。
「何よりも問題分析のフェイズでは、自ら考えることが重要だが、すべて自己流では成長するのに時間がかかる。まずは既存の方法論を学び、そこから自分のスタイルを確立させていくといい」と山崎氏は強調する。
 |
| 実践で学んだことと基本原則(方法論)のマッピング。プロマネを目指す人にはこのマインドが不可欠ですね |
さらに、「実践にかなう勉強はありません。困難だったことの原因が何であるかを分析し、次の機会までに習得し、スキルを補強しておく。また、実践で学んだことと基本原則(方法論)をきちっとマッピングする姿勢が大事。こうしたマインドがプロマネを目指す人には不可欠」という。
理論は数多くあるが、形よりも“マインドが大事”と強調する山崎氏。「プロジェクトを率いる人間はプロセスの形だけにこだわる必要はなく、どういうプロセスが必要かという意識が大切です。特にプロジェクト管理ではリスク感覚が重要なファクターになります」
というのも、リスクへの意識がプロセスを動かし、アクティビティを割り振ることになる。リスク管理はプロセスのあり方から人の配置までにも影響するからだ。
「リスクに的確に気を配ることができれば、大きな問題は表面化しません。リスクへの意識が不完全だと失敗します。例えばアクティビティの優先順位付けなどには注意を払う必要があります」
| プロマネは「ピッチの外にいる監督」 エンジニアの自主性を引き出せ! |
また、リスク感覚に加え、プロマネにはサッカーならピッチの外にいる監督のような資質が求められるという。
「部下であるエンジニアの能力を後押しする素養が欠かせません。直接ボールをけるプレーヤーが自分で状況判断して最適なパスを出すかのように、プロマネはエンジニアの自主性を促し、彼らが能力を発揮しやすくなるような環境を整備する必要があるのです。その素養を持つ人は、プロマネとして飛躍できるのではないでしょうか」
 |
| 独自のスタイルを行使できる自由なカルチャー。マネジメントのキャリアを積むには、最適な環境といえる |
実際にテンアートニで働く現役プロマネたちを見ると、実に個性豊かだ。それぞれ個々のスタイルを確立し活躍している。また独自のスタイルを行使できる自由な雰囲気がテンアートニにはある。
「プロマネが対峙するのは結局人間です。人間と対峙する際はその態度が個性として表れるのです。テンアートニで働くプロマネは、みな独自のマネジメントスタイルを極めている人ばかり。これはしっかりした基本原則が身に付いているからできることです。プロジェクトの上流工程にもかかわることができ、マネジメント力を鍛えられる環境があります」
こうした環境でマネジメントのキャリアを積むことは、マネジメント経験がある人はもちろんのこと、将来の“プロマネ予備軍”にとっても、その後のエンジニア人生を実り多いものにしてくれるだろう。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集要項 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
株式会社テンアートニ
企画:アットマーク・アイティ人財局
制作:アットマーク・アイティ編集局
掲載内容有効期限:2004年12月31日
| 関連記事リンク |
| ・Java Solution FAQ (Java Solution) ・[検証実験]Webシステム開発の効率化を検証する (Java Solution) ・[Javaを拓く人々]フレームワークでWeb開発を効率化 (Java Solution) ・Linuxビジネスの真髄は"ブランド"にあり、テンアートニ (@ITNews) ・ゼンド・オープンシステムズ本格稼働 (@ITNews) ・レッドハット、基幹システム攻略へ進軍を開始 (@ITNews) ・プロダクトレビュー[Zend Studio 2.5 日本語版] (Linux Square) ・転職。決断のとき(転職研究室) ・プロジェクトリーダーの条件(注目企業研究) |
| 企業情報 |
| 株式会社テンアートニ(現サイオステクノロジー株式会社) 設立 平成9年5月23日 代表者 代表取締役社長 喜多 伸夫 資本金 7億5001万5千円 従業員数 110名(平成16年4月現在) 本社所在地 東京都千代田区外神田2-15-2 新神田ビル 事業内容 ・JavaによるWebシステム構築 ・Linuxによるシステムインテグレーションおよび製品販売 |
| 待遇 |
| 給与 前職での経験・能力などを充分考慮のうえ、当社規程により決定 勤務時間 9:00〜17:30 休日・休暇 完全週休2日制、祝日、年末年始、慶弔、誕生日休暇、半休制度あり 勤務地 東京(千代田区外神田) 福利厚生 交通費全額支給、各種社会保険完備、報奨金制度、財形貯蓄制度、大塚商会の福利厚生施設(保養所、直営リゾートホテル、国内外特約ホテル)利用可能 |