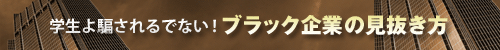
第2回 ネットや雑誌からの情報収集でブラック企業を見抜く
新田龍(ブラック企業アナリスト)
2009/11/30
■求人情報からブラック企業を見抜く
(1)求人広告を長期間にわたって掲載している
⇒退職者が多い可能性があります。
普通、採用活動というものは「人員計画を立てて採用活動を行い、充足したら終了する」ものです。しかし一部では、3月末ギリギリまで採用(新卒の場合)していたり、1年中採用(中途の場合)している会社が見受けられます。
恐らくその会社には何かしら、内定を辞退されたり、人が辞めていったりするような要素があり、常に人員を補充していないと間に合わないくらいの事情があるのでしょう。研修が厳しいのか、仕事がつらいのか、社風がよくないのか、その全部か……。「求人広告常連企業は要注意」するに越したことはありません。
(2)ハードルの低さが強調されている
⇒人が集まらない会社、もしくは(人が集まりにくい)仕事内容である可能性があります。
キーワードは「ノルマなし!」「知識ゼロでもOK!」「難しくない仕事です!」など。いくら社会人経験のない新卒社員を採用するといっても、ある程度の素養や知識経験は求められるものです。そうではない場合は、どこかに「そうまでして採用しなければならない理由がある」と考えてよいでしょう。スキルにならないルーティンワークか、はたまたものすごいハードワークか……。いずれにせよ、「なぜそうなのか?」というポイントを確認しておく必要がありますね。
(3)給与が異常に高い
⇒ハードワークか、高い歩合給が設定されている可能性が高いです。
| エンジニアライフ コラムニスト募集中! |
あなたも@ITでコラムを書いてみないか 自分のスキル・キャリアの棚卸し、勉強会のレポート、 プロとしてのアドバイス……書くことは無限にある! コードもコラムも書けるエンジニアになりたい挑戦者からの応募、絶賛受付中 |
一般的に、大学学部卒の初任給といえば月額20万円前後です。ところが、外資系の金融会社やコンサルティング会社ではなく、国内の一般的な企業で30万円程度の初任給を設定している会社があります。その会社に入れば誰でも高給をとれるのでしょうか? あいにくそうではなく、「異様にレベルが高く、ハードな仕事への対価」であるか、「トップ営業のモデル賃金」といった条件付きの金額である場合がほとんどです。それだけの給与を得るためには、相応の努力と実績が必要なはずですから、「果たして自分にできるのか?」「それだけの適性がありそうか?」と自身に問い掛けておきましょう。
(4)仕事内容が「よく分からない横文字」
⇒人気がない/後ろめたい仕事であることを隠している可能性があります。
募集に苦労する職種ほど、特に意味もなく「コンサルティング」「マーケティング」といったフレーズが多用されるようです。なので、このような抽象的なキーワードが出てきたら「怪しい……」と感じていただくと共に、「商材は何か?」「具体的に何をするのか?」をキチンと確認されることをお勧めします。
(5)社員数に対して、求人人数が多い
⇒退職者が多く、入社後のマネジメントも手薄である可能性があります。
目安としては、一度に採用する人数が全社員数の20%を超える規模だと多い部類に入ります。入社後何らかの理由で辞める人が多く、それを見積もったうえで設定した人数である可能性がありますね。バランス的に不自然な人数の採用を行っている企業は、必然的に「入社してきた社員をきちんと教育・管理できる人が少ない」状況にもなってしまいます。仕事のフォローやマネジメントが薄くなってしまうような環境では、個々人の成長のチャンスを逃してしまう可能性がありますし、評価の目が行き届かないことで、昇進、昇給の機会まで逃がしてしまうかもしれません。
■企業のWebサイトからブラック企業を見抜く
(1)Webサイトが稚拙である
⇒社員の能力レベルが低い可能性があります。
IT化が進展した現在において、企業の顔ともいえるWebサイトがきちんと管理できていないのは、それがまずいことだと気付ける社員がいないか、いたとしても改善できないなんらかの理由(金銭的、内部体制的など)があることが考えられます。気にしておくべきポイントとしては、
・誤字・脱字がある
・文法的におかしい文章構成
・更新頻度が低い
・すでに終了したセミナーなどの案内を載せている
・見にくく、使いにくい
・会社情報をみても、何の会社かよくわからない
といった点が挙げられます
(2)必要以上に「社風の良さ」が強調されている
⇒それ以外にアピールできる要素がない可能性が高いです。
自社の製品やサービスに何かしらの強みがあって、市場でアドバンテージをとれるものであれば、そのようにアピールするはず。しかし強みが何もない場合、最後の砦は「いい雰囲気」だけ、ということになります。企業サイトの採用情報欄などで、社員全員の集合写真や、楽しそうに笑顔やガッツポーズを振りまいている社員が載っているものがよい例です。そのような会社では、社風以外でよりどころにできる強みがある会社かどうか、シッカリ確認してみてください。
■インターネットサイトからブラック企業を見抜く
・ネット上でブラックの噂がたっている
⇒不満を持った社員が多くいる可能性があります
検索サイトで社名を入力すると、その会社のホームページ以外にもいろいろな候補が出てくるはずです。会社によっては2ページ目以降くらいから、ひどい場合は1ページ目のトップに近い位置に、「●●って会社どうですか?」「●●は要注意!」といった「ブラックな噂」が出てくることがあります。
またGoogleであれば、検索結果の上もしくは下の方に「他のキーワード」として、社名と一緒によく検索されているキーワードの組み合わせが出てきますが、その中に「噂」「評判」「2ch」、分かりやすいところで「ブラック」といった言葉は出ていませんか。そういった言葉が合わせて検索されているということは、それだけなんらかの噂があって、気にされていることの現われといえます。もちろん、あくまで噂ですから真偽は不明ですし、その企業の何がブラックだといわれているのか、それは自分自身の価値観と照らし合わせてどうなのか、といった点について確認する必要があります。
■まとめ:どう解釈するかが重要
「ブラック企業」の兆候は上記のどおり、入社前でもある程度見抜くことができるのです。しかし一方で、それらの情報はあくまでその企業の一面でしかない、というのもまた事実。常に求人を出していたり、採用基準が低い会社の中にも、「業績が絶好調で人手が足りない。未経験者でもキチンと教育する!」といった心意気のあるところが混じっているかもしれません。自分自身の価値観と合致しているなら、その会社は自分にとってはブラックではありません。立派なキャリアステップなのです。
ブラック企業らしい兆候に対しては、「この会社ブラックだ!」と糾弾するのではなく、「なぜそうなっているのだろうか?」と情報を解釈する、「本質を考えるクセ」を持たれることをお勧めします。
| 筆者プロフィール | |
| 新田龍(にった りょう) ブラック企業アナリスト、キャリア教育プロデューサー、大学講師、株式会社就活総合研究所 代表取締役、および株式会社ヴィベアータ 代表取締役。 |
|
| 早稲田大学政治経済学部卒業後、ネット上で「ブラック企業」といわれる2社において事業企画、コンサルタント、人事採用職を経て独立。「すべてのはたらくひとをハッピーに」を目指し、これまで5000人以上の面接・カウンセリング経験、早稲田大学など20大学でのキャリア指導経験を持つ。著書に『人生を無駄にしない会社の選び方』、(日本実業出版社)がある。 |  |
@IT自分戦略研究所は2014年2月、@ITのフォーラムになりました。
現在ご覧いただいている記事は、既掲載記事をアーカイブ化したものです。新着記事は、 新しくなったトップページよりご覧ください。
これからも、@IT自分戦略研究所をよろしくお願いいたします。
