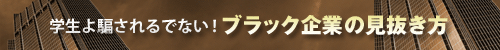
第5回 「自分の価値観」を探り、後悔のない会社選びを
新田龍(ブラック企業アナリスト)
2010/2/24
■ メディアや周りに流されない自分の価値観の見つけ方
昨今は景気悪化が叫ばれ、なんとなく「大手」「安定」といったキーワードが望まれる傾向にあります。しかし、「自分に合った会社」は人それぞれです。先ほどの「知名度」や「人気ランキング」にしても、それらの要素が自分にとって本当に大事であればいいのですが、メディアや周囲の影響で、知らず知らずのうちに「そう思わされているだけ」という可能性は否定できません。
「外部から思わされていること」と「自分自身が本当に大事にしたいこと」にギャップがある状態で就職先を選択してしまい、入社後ミスマッチに気付く、といった事例を数多く見てきました。読者の皆さんには、そのような事態になっていただきたくないと考えています。
ここでいう「自分が大事にしたいこと」こそ、イコール「自分自身の価値観」であるといえます。「価値観」を探るというと難しく感じるかもしれませんが、次の3つの要素に分けて考えると分かりやすいでしょう。
- 自分は何をやりたいのか=WANT
- 自分は何ができるのか=CAN
- 自分は何をしなければならないのか=MUST
この要素を図示したものは、皆さんもご覧になったことがあるかもしれません。
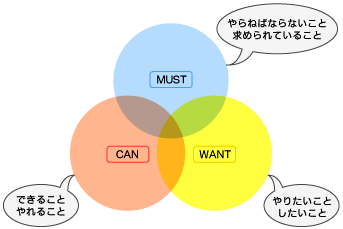 |
図1 WANT/CAN/MUST |
この3つのバランスを取れるところが、自分にとって心地よい領域というわけです。このうち「WANT」と「CAN」は自分の意思ですが、「MUST」は会社や組織の意思ですね。
「WANT」について、すでに「やりたい仕事」が決まっている場合は問題ありませんが、そうでない場合は多少の分析が必要です。これまでの経験の中で、楽しめたこと、やりがいを感じたことを思い返し、「そう感じた要素は何だったか?」と考えてみてください。その要素が共通しているビジネスであれば、充実感を持って取り組めるはずです。
| エンジニアライフ コラムニスト募集中! |
あなたも@ITでコラムを書いてみないか 自分のスキル・キャリアの棚卸し、勉強会のレポート、 プロとしてのアドバイス……書くことは無限にある! コードもコラムも書けるエンジニアになりたい挑戦者からの応募、絶賛受付中 |
「CAN」は、これまでの経験から導き出せるはずです。目標を設定してやり遂げたこと、組織の中で果たせた役割は何でしょうか。
「MUST」は、「企業理念」や「求める人物像」とのマッチングであるといえます。企業のWebサイトを見たり、説明会で話を聞いたりすれば分かります。
ちなみに会社が給料を払うのは、皆さんの「やりたいこと」に対してではなく、「できること」に対してである、という事実を認識することは重要です。逆にいうと、「高い給与を得たい」「活躍したい」ということであれば、まずは自分ができることをより多く提供できるようになることが必要です。また、それこそが「キャリア」をつくる基本になります。
いずれにせよ、この判断基準は純粋に個人的なものですので、周囲の意見にとらわれず、主観を大事にして考えましょう。要素別に見れば、いわゆる大手有名一流ブランド企業よりも、そうでない企業に強みがあったり、面白い仕事ができたりするところがあります。本来、企業選びにはさまざまな基準があるはず。多くの選択肢がある新卒就職のタイミングで、ぜひ幅広い視野を持って検討してください。その会社で仕事をしていくのは、ほかでもない自分自身なのですから(もちろん、その会社が「ブラック企業」かどうかは、過去の記事を参考に、きちんと見抜いてくださいね)。
■ 会社選びの際のチェックポイント(Why so?/So what?)
求人サイトを見ていて、いかにも条件が良さそうな会社が見つかったとしましょう。そのときはぜひ「Why so?」(なぜそうなっているのか?)、そして「So what?」(だから何なのか?)という疑問を持ってみることをお勧めします。そうすることで、報われないブラック企業に引き込まれるリスクを、少しでも回避することができるかもしれません。
● 「Why so?」の例
- 「その会社はなぜ、社員1人当たり年間1億円以上も売り上げをあげられるのか?」
- 特許など知的財産からの権利収入がある?
- それとも違法なビジネスに手を染めている?
- 「その会社の平均年収はなぜ1000万円を超えているのか?」
- 付加価値が高くて利益を稼げる商材がある?
- それとも厳しいノルマによるインセンティブ収入?
- 「なぜこんな創業間もない会社が、この立地にオフィスを構えられるのか?」
- 独自のビジネスモデルで高収益を見込める?
- それとも単なるコネ?
● 「So what?」の例
- 「1人当たりの粗利額が年間で500万円もない」
- ということは、給料の伸びは……。
- 「取引先の売上高比率を見ると、A社が45%を占めている」
- もし何かの理由で、A社との取引がなくなると……。
- 「社長は『株式公開が目標だ』といっていた」
- それがゴールだと思っているとすると、その後の展開は……。
少し深掘りして考えるだけでも、新しい視野が開けてくることになるでしょう。「理想の会社」と見えるところには、その裏返しになっている「厳しい現実」が存在するかもしれません。それらを踏まえたうえで、納得できる理由があれば前向きに検討すればいいですし、どう考えても難しい、ということであれば、ほかの会社を探せばいいのです。
もしかしたら、「100%自分に合った会社」は存在しないかもしれません。しかし、われわれには物事を解釈し、意思を持って行動する力があります。
ある会社に入って、そこで仕事をする。その事実は同じ会社にいる誰にとっても同様ですが、それを単に「やらされている」と感じて受け身で過ごすのか、「この環境を利用して、面白く過ごしてやろう」と考えて積極的に行動するかで、仕事の意味合いはまったくといっていいほど変わります。「場所」は変わらなくとも、「場」はいかようにも生かせるのです。
■ 連載のまとめ
人はつい「労働」を「消費」と同じように考えてしまうことがあります。消費であれば、自分がお金を払ったものに対して、すぐに対価となるサービスやモノが提供され、その満足度で割に合うか合わないかが判断できます。でも、労働は本質的にまったく違うものです。
労働の対価は、創出した価値と同じではありません。その効用が確認できるのは、10年後、「あのときの経験は無駄でなかった」と感じるときかもしれません。「働く」ということは、そのような長期的視点でとらえる必要があります。「割に合うか、合わないか」だけで判断してしまっては、結局、得るものも得られなくなるでしょう。
筆者自身がこれまで人の「キャリア」を支援する仕事にかかわり、痛感しているのは、
「キャリアに勝ち負けはなく、正解もない」
「あるのは自分にとってハッピーなキャリアか、そうでないキャリアかだけ」
だということです。
他人の価値観に従ったり、他人のまねをしても意味がありません。それよりも、自分自身がどんな価値観を持っているのかという、心底からの動機や意欲の源を知り、「本来の自分に合った」道を進むことがハッピーなキャリアであると考えます。
内定はゴールではなく、キャリアのスタート。これまで解説したことを参考に、皆さんそれぞれが自分にとってハッピーなキャリアを歩んでいかれることを祈っています。
| 筆者プロフィール | |
| 新田龍(にった りょう) ブラック企業アナリスト、キャリア教育プロデューサー、大学講師、株式会社就活総合研究所 代表取締役、および株式会社ヴィベアータ 代表取締役。 |
|
| 早稲田大学政治経済学部卒業後、ネット上で「ブラック企業」といわれる2社において事業企画、コンサルタント、人事採用職を経て独立。「すべてのはたらくひとをハッピーに」を目指し、これまで5000人以上の面接・カウンセリング経験、早稲田大学など20大学でのキャリア指導経験を持つ。著書に『人生を無駄にしない会社の選び方』、(日本実業出版社)がある。 |  |
@IT自分戦略研究所は2014年2月、@ITのフォーラムになりました。
現在ご覧いただいている記事は、既掲載記事をアーカイブ化したものです。新着記事は、 新しくなったトップページよりご覧ください。
これからも、@IT自分戦略研究所をよろしくお願いいたします。
